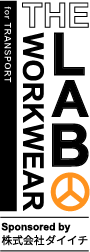作業着の運用を支える着用ルールの考え方
このサイトは企業向けオーダーメイド作業着の企画・製造・販売を展開する株式会社ダイイチをスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
 目次
目次
作業服の着用ルールはなぜ必要なのか
作業服は単に「その会社の社員であること」を示す服ではありません。従業員の安全を守り、効率的に作業をするためのツール、そして企業の採用力向上、イメージアップを図るためのツールです。このため正しいルールのもとで着用しないと、本来の目的を果たすことができません。
たとえば、外灯の少ない夜間作業が多い現場で視認性の高い作業服を支給しているのに、きちんと着用されなかったらどうなるでしょうか。行き交う大型車両に認知されず、事故のリスクが高まってしまいます。また、衛生管理が必要な現場で帽子やマスクが正しく着用されないと、異物が混入するかもしれません。
作業服を有効に運用するためには、着用ルールが必要不可欠。社内でしっかりと検討して、作業員に周知させることが大切です。
徹底したい着用ルール
着用ルールは、作業服の着用方法だけでなく、安全性・統一感・快適性・運用のしやすさなど、さまざまな角度から考慮することが重要です。一般的に重視したい着用ルールは、以下の3つです。
自分の体に合ったサイズを着用する
作業服は、体に合ったものを着用することが大切です。キツすぎる・緩すぎる作業服では、仕事に集中できなかったりストレスを感じたりしてしまいます。また、通気性や速乾性などせっかくの機能が十分に発揮されない場合があります。
特にオーバーサイズの作業服は、機械への巻き込み、足元が見えず転倒するなどリスクが高まるので要注意。場合によっては大事故につながるため、体型を考慮してサイズ選びを行いましょう。
アレンジせず正しく着用する
上着の袖口ボタンをしっかり留める、上着の裾をボトムスに入れるなど、制服は正しく着用しなくてはなりません。防炎、帯電防止、高視認性などの機能は、正しく着用して初めて効果を発揮します。腕まくりや上着の裾が出た状態は、機械への巻き込み、火傷、薬品飛散、紫外線曝露などのリスクを高めてしまいます。
何より、全員の着用方法が揃っていないと、統一感や清潔感を感じられません。「だらしない」「着用ルールも徹底できない」会社として信頼性やイメージが損なわれてしまいます。
ほころびはすぐに直し、清潔な状態を保つ
長く着用していると、破れや穴、ほつれ、シミ汚れなどが生じることがあります。ほころびをそのままにしておくと、製品や機械に引っかかったり火花が飛んだりする可能性があります。また、汚れによって悪臭や肌トラブルが生じることも。ほころびや汚れを見つけたらすぐに修繕するか、必要に応じて買い替えを検討しましょう。
着用ルールを周知・徹底させる方法は
「作業服を現場で着用してもらえない」「勝手にアレンジされている」「ルールが形骸化している」など、作業服の着用方法に課題がある場合は、作業服を導入した目的やルールが曖昧になっているかもしれません。 着用ルールを見直し、ルールを周知するとともに、「なぜ着用ルールを守らなければならないのか」「ルールを守らずに作業をした場合どうなるか」を説明してみてください。必要に応じて説明会や勉強会などを開くのがおすすめです。
ダイイチなら、作業服のデザインだけでなく、現場と経営の両方の視点に立った運用方法を提案。導入後も社員からの意見を継続的に収集し、運用の改善をサポートしてくれます。
企業向けユニフォームの
株式会社ダイイチ
運送業は、モノを運ぶだけの仕事ではありません。時間を守り、安全を守り、人と社会をつなぐ誇りある仕事です。だからこそ、現場で働く人が安心して動けること、そしてその作業着に誇りを持てることが重要です。私たちダイイチは、快適性・機能性・デザイン性を兼ね備えた一着で、働く人の力を引き出し、“運ぶチカラ”の進化を支えていきます。

柳下 元紀さん